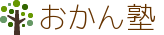【営業時間】平日・土曜 9:30〜16:30
- ホーム
- 今日のおかん塾
今日のおかん塾
- 受講生の感想
- コラム
- 講座レポート
- はじめての方へ
- 事例
- つぶやき
- 辛口
- 高校生
- 中学生
- 小学生
- 幼/園児
- 発達障がい
- 聞き方
- 育児の原則
- ネット依存
- 成績不振
- 育児の自信喪失
- 癇癪・ぐずり
- 心身症
- 過干渉
- 会話ができない
自分が傷つくことを、恐れない「わたし」になろう
2025/09/12
ほんとうの気持ちって何だろう
ほんとうの気持ちって、苦しいモノなのかな?
いやだ、
やめてほしい
うざい?
めんどう?
腹がたつ?
いろいろあるけど、それって駄目なことなのかな?
言ってはいけないのかな?
よーく見てみると、もっともっと奥にあるほんとうの気持ちが浮かんでくるよ。
気持ちってミルフィーユみたいに、重なっているのかな。
ほんとうの気持ちが傷つかないように、たくさんの防御服…
続き
ほんとうの気持ちって、苦しいモノなのかな?
いやだ、
やめてほしい
うざい?
めんどう?
腹がたつ?
いろいろあるけど、それって駄目なことなのかな?
言ってはいけないのかな?
よーく見てみると、もっともっと奥にあるほんとうの気持ちが浮かんでくるよ。
気持ちってミルフィーユみたいに、重なっているのかな。
ほんとうの気持ちが傷つかないように、たくさんの防御服…
授業中に集中できない生徒に、教師はどう対応する?
2025/09/10
「先生、なんか集中できません」
「つまらない」
「疲れた」
教室で日常的に耳にするこんな言葉。
あるいは、言葉に出さなくても、机に突っ伏したり、落書きばかりしたり、隣とおしゃべりに夢中になったり…。
教師であれば誰しも、「どうすればいいのだろう」と悩む場面ですよね。
多くの先生はこう考えます。
「もっと工夫して授業を面白くしなければ」
「注意して集中させなければ」
「このままでは学力が落ち…
続き
「つまらない」
「疲れた」
教室で日常的に耳にするこんな言葉。
あるいは、言葉に出さなくても、机に突っ伏したり、落書きばかりしたり、隣とおしゃべりに夢中になったり…。
教師であれば誰しも、「どうすればいいのだろう」と悩む場面ですよね。
多くの先生はこう考えます。
「もっと工夫して授業を面白くしなければ」
「注意して集中させなければ」
「このままでは学力が落ち…
教師学って何? ― 現場の先生が求めているもの
2025/09/08
教師の仕事は、この数十年で大きく様変わりしました。
膨大な事務作業や部活動指導がニュースに取り上げられる一方で、実際に先生を最も疲弊させるのは「人間関係」ではないでしょうか。
生徒とのやりとり、保護者との関係。
努力が伝わらず、信頼が築けないとき、教師は深いストレスや虚無感に襲われます。
逆に、もし良好な関係性があれば——。
多少の忙しさもやる気やアイデアに変わり、仲間と共に困難を乗り越え…
続き
膨大な事務作業や部活動指導がニュースに取り上げられる一方で、実際に先生を最も疲弊させるのは「人間関係」ではないでしょうか。
生徒とのやりとり、保護者との関係。
努力が伝わらず、信頼が築けないとき、教師は深いストレスや虚無感に襲われます。
逆に、もし良好な関係性があれば——。
多少の忙しさもやる気やアイデアに変わり、仲間と共に困難を乗り越え…
関連エントリー
-
 おかん塾の子育て
3人の息子がいても、いつの間にか“親バカ”になれた秘訣
おかん塾の子育て
3人の息子がいても、いつの間にか“親バカ”になれた秘訣
-
 講座レポート
「え?こんなに違う?」目からウロコの講座レポート満載 おかんの仕事は365日24時間(-_-;)ずっ
講座レポート
「え?こんなに違う?」目からウロコの講座レポート満載 おかんの仕事は365日24時間(-_-;)ずっ
-
 つい怒ってしまうから抜け出す3日間
おはようございます。今日は、朝から整形外科クリニックの診察に行ってきました。実は、先日の1月15日に
つい怒ってしまうから抜け出す3日間
おはようございます。今日は、朝から整形外科クリニックの診察に行ってきました。実は、先日の1月15日に
-
 主体的で自由な大人の学び
親業訓練講座は全8回です。毎回、宿題が出ますが、提出は「自由」です。大人の勉強は強制されることはあり
主体的で自由な大人の学び
親業訓練講座は全8回です。毎回、宿題が出ますが、提出は「自由」です。大人の勉強は強制されることはあり
-
 「勉強しない高校生へ」しっかり啖呵を切れる母になろう
親業訓練講座の第4回目のレッスンが終わりました。 3週間ぶりの講座だったので、みなさんは「お久しぶり
「勉強しない高校生へ」しっかり啖呵を切れる母になろう
親業訓練講座の第4回目のレッスンが終わりました。 3週間ぶりの講座だったので、みなさんは「お久しぶり
-
 子どもを変えない子育てが、子どもを変える理由
今日は、夫のお休みの日。念願の廣田神社(兵庫県西宮市)にお参りに行ってきました。私が捻挫をしちゃった
子どもを変えない子育てが、子どもを変える理由
今日は、夫のお休みの日。念願の廣田神社(兵庫県西宮市)にお参りに行ってきました。私が捻挫をしちゃった
-
 塾に払うお金がもったいないからやめてくれる?と言いたい時
塾にいかない、サボる「行く行く」と言いながら、「行かない」「止めたら?」というと「止めたくない」と
塾に払うお金がもったいないからやめてくれる?と言いたい時
塾にいかない、サボる「行く行く」と言いながら、「行かない」「止めたら?」というと「止めたくない」と
-
 親に何も言う気がしなくなる12パターンの言い方
親が言ってないつもりでも、言っている「小言」子どもが話しをしない、話しかけても、スルーされる、調子の
親に何も言う気がしなくなる12パターンの言い方
親が言ってないつもりでも、言っている「小言」子どもが話しをしない、話しかけても、スルーされる、調子の