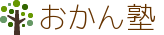- ホーム
- おかん塾の子育て
- 受験・学校生活の乗り越え方
- 高校生の娘が帰ってこないで警察沙汰になった後、考えておきたい“親のあり方”
高校生の娘が帰ってこないで警察沙汰になった後、考えておきたい“親のあり方”

高校生の娘が、家を出て夜中になっても帰ってこない時、警察に相談することはよくあるかもしれません。
以前、ある受講生の方から、「夜中に家出騒ぎを起こした高校生の娘さん」へのかかわり方について相談を受けました。
「家出騒ぎ」を起こした子どもを前にして、感情もそう簡単に収まりませんよね。
「どれほど心配したと思ってるの?」「こんなに考えているのに」と、自分の感情をぶつけてしまいそうになります。
ですが、それだけではまったく解決しない―
そのことを、今までの経験から身に染みているのかもしれません。
1、親には感情が抑えられない時がある
親も辛いから「悪者」を決めたくなる
昨日、娘が夜中になっても帰って来ず、警察に相談する事態になりました。夜中の1時過ぎには自分で帰ってきたのですが、家を出る直前に日記を処分し、身分証明を全部置いて行きました。
日記は墨で汚れてよく見えませんが、毎日辛いと書いてありました。精神的な疾患を疑っているようです。
「帰りが遅くなったので心配」とは伝えました。しかし、命を盾にするような方法が受け入れられず、優しい言葉をかける気になれません。
本人も色々と悩んでいるとは思いますが、このような方法を取られると、関わる全ての人が踏み込んでいけません。
しかし、ここでこちらが折れるべきでしょうか?それは第2法(放任・甘やかし)になるのでしょうか?
私としては子供の問題と考え、こちらから働きかけしたくありませんが、病気の場合は別でしょうか?
どうしても話しをしたくないのです。色々と考えていますが、答えが出ません。
メールをありがとうございました。
私は、ここが親子関係の一番むずかしくて、こじれやすいところだと思っています。
相手のツラサも痛いほど感じるけど、自分もツラくてどうすることもできない時、人は自分の無力感に苦しくなります。
そしてその感情を感じるほどに、怒りに変わってくるのです。
でも、怒りの感情に支配されているだけでは、それでは一向に解決しません。
だって、そのツラサや怒りの大元にあるのは、まぎれもなく「わかってもらえない苦しさ」だから。
すなわち「伝わっていない」「わかってもらえていない」という行き詰った感覚が、親子をさらに苦しくしているのだと思います。
原因追及思考から、問題解決思考へ
怒りの渦中にいるからこそ考え抜きたい、自分のどんな気持ちが溢れてくるのか?
怒りの中に埋もれている、自分の本当の気持ちは何か?
今回も、娘さんの「命を盾に取るような方法」との記述はこの方の「先入観が入った」捉え方です。これをそのまま使っていては、伝わるものも伝わりません(-_-;)
「具体的にはどんな行動ですか?」とお伝えしたら、次のように返ってきました。
色々な事を書き出して考えてみました。
何を感じているか、
どんな事をしてあげたほうがいいと思ってるか、でもできない気持ちとか。
具体的には?との問いに、
客観的事実は遅く帰ってきたというだけだった!と気づきました。
今までの行動から、私が勝手に「命を盾にしてる」と思い込んでいたかもしれません。
でもそこが1番心配してる所なので、それが保証されれば、子供の問題として、見守れると思いました。
ちょっと整理されました。ありがとうございました。
事実を客観的に見れたことで、状況を整理できて、少し落ち着いてきましたね。
「命を盾に取るような方法」に見えた態度は、ただ「遅く帰ってきた」という事実が浮かび上がってきました。
これは、本当に心配しているからこそ、そう思えてしまうもの。
これこそ、愛するがゆえの反応!そのものですよね。この気持ちも事実ですから、場合によっては伝えてもいいと思います。
何より、無事でよかったですね。ホッ
2、親としてどうしたらいいか?わからずに悩む時
あれで良かったのか?次回につながる検証のススメ
自分の気持ちを整理しておくと、次回に、同じような展開になった時に慌てずに済みます。
あなたにとっては、命を楯にしているように感じることが、一番堪えることであるし辛いことなら、それを率直に伝えることもできますね。
伝える言葉は、もちろん、親業の「わたしメッセージ」が必須です。相手に誤解をされない伝え方が学べます。ぜひ講座で学んでください。
ホンモノの血の通ったコトバだけが子どもの胸に届きます。こういう時に「あなたメッセージ」はありえませんので注意してください。
親の在り方を子どもに問われる時
子育てにはこういう「修羅場」みたいなときが、時々あるようです。
親としての覚悟とかあり方を問われる時ですね。
この時こそ、河合隼雄先生のコトバを借りると、100点をめざしたい時なのかな、って思います。
「100点以外はダメなときがある」
 |
こころの処方箋 (新潮文庫)
529円
Amazon |
模範解答はない。自分の持っているだけのものを、全力をあげてぶっつけてみるのだ。
そこにはじめて本当の対話が生まれる。
(中略)
人生にもここぞというときがある。
それはそれほど回数の多いものではない。
ともすると、そのときに準備も十分にせず、覚悟もきめずに臨むのは、まったく馬鹿げている。(こころの処方箋 12 より)
人生には、80点ではダメで、98点でもダメで、100点でなければ、ダメなときがある、というのです。
ひょえ〜厳しいですね
そして、ここでの100点とは「満点」を狙う!みたいな、「いい点」を取るものではなく、自分の持っているだけのものを、全力をあげてぶつかり本当の対話をすること。
準備できるものは十分に準備して、自分の持てる力を発揮できるように、覚悟を決めて、対話に臨むことだと思います。
「これしかない」と自覚があるかないかで、結果は大いに違ってくるそうです。
まさに、人間関係の真実の瞬間ですね!
ちなみに、河合先生の言葉を借りると、100点はいつも取り続けるものでもないのですよ。いつもは、「ヘタレおかん」でいいってことね(笑)
【参考記事】子どもをガミガミ叱ってばかりで自己嫌悪に陥っているあなたへ伝えたいコト
3、親の学びとは子どもが自分と違う葛藤を受け入れること
自分のコトバが言えるように練習する
おかん塾でも親業訓練一般講座や自己実現のための人間関係講座で、内外一致の「わたしメッセージ」は何度も何度も復習しています。
ほとんどの人は「ほんとうの感情」を見つけることに慣れていません。
でも、練習していくと、はじめは「イヤ」だけの感情だったのが、「情けない」や「もどかしい」「やるせない」などの感情がハッキリとみえてきます。
さらに、丁寧に感情を紐解いていくと、他の感情も少しずつ見えてきます。そしたら、「本当の問題点」がわかってきますから、スッキリとクリアになっていきます。
こういう作業の経験がない方が多いからこそ、トレーニングがおススメです。
「今までこんなこと考えた事が無かった」「自分の気持ちを考えるのが難しい」と言われますが、感情の整理がしっかりとできていると、ブレずに過不足のないコトバを、自信をもって伝えられますよ。
親業の方法で作るコトバは、内外一致してて、迫力がありますから、子どもの心に素直に届きやすいです。
葛藤を内包するのが大人であること
河合先生の本に「葛藤を抱え続けられるというのがおとなの条件」という深い言葉があります。
子どもを尊重したいけど、でも現実には、子どもの身勝手な行動が許せないという「相反する気持ち」はが付き纏います。
頭では理解しているけれど、いざとなると、想定外の事件に不安を感じてしまうときの「葛藤」こそが、子育ての一番の苦しさ。
おかん力とは、葛藤力をどれだけ持ち続けられるか?なのかもしれません。
それは、人として成長できるチャンス!です。
人はぶつかる事でも成長します。
自分が苦手で避けたいと思っていることは、子どもにも教えらません。
だから「ケンカ」が苦手だし、人間関係やコミュニケーションがますます苦手になっていく人が増える原因になっていくと思うんですよね。トホホ
-
 勉強しない高校生にどう関わる?やる気を無くす本当の理由と親だからできる関わり方
高校生の息子が勉強しなくなった…このまま放っておいてもいいの?どうしてうちの子は、真面目に勉強しない
勉強しない高校生にどう関わる?やる気を無くす本当の理由と親だからできる関わり方
高校生の息子が勉強しなくなった…このまま放っておいてもいいの?どうしてうちの子は、真面目に勉強しない
-
 「学校に行きたくない」小学生の娘に言われても慌てずにすむ必須スキル
「明日、小学校に行きたくない」 急に子どもにそう言われたら、ビックリしますよね。「不登校」と言うワー
「学校に行きたくない」小学生の娘に言われても慌てずにすむ必須スキル
「明日、小学校に行きたくない」 急に子どもにそう言われたら、ビックリしますよね。「不登校」と言うワー
-
 夏休みも大詰めなのに宿題が終わらない!イライラするその時の我が家のリアル
毎年、お盆を過ぎる頃に夏休みの宿題でモンモンとしていませんか? 夏休みや冬休みなど、長期休暇の宿題を
夏休みも大詰めなのに宿題が終わらない!イライラするその時の我が家のリアル
毎年、お盆を過ぎる頃に夏休みの宿題でモンモンとしていませんか? 夏休みや冬休みなど、長期休暇の宿題を
-
 プライドが高く繊細な思春期男子にどう接する?「自尊心」を壊さず地雷を踏まないコツ
思春期の男子の謎(?_?)のひとつ。プライドは果てしな~~~く高いのに、ハートは実はかなり繊細でチキ
プライドが高く繊細な思春期男子にどう接する?「自尊心」を壊さず地雷を踏まないコツ
思春期の男子の謎(?_?)のひとつ。プライドは果てしな~~~く高いのに、ハートは実はかなり繊細でチキ
-
 イライラが止まらないのは伝えきれていないから!言いたいことを伝える秘策と道のり
子育ての悩みの鉄板!「イライラが止まらない」。イライラは、慢性的になってしまうともやは自分では手が付
イライラが止まらないのは伝えきれていないから!言いたいことを伝える秘策と道のり
子育ての悩みの鉄板!「イライラが止まらない」。イライラは、慢性的になってしまうともやは自分では手が付
-
 「ダメな母親でごめんね」親として自信がないあなたへ贈りたい信頼を取り戻す親業メソッド
「子供に申し訳ない」「こんな母親でごめんね」「私ってダメな母親だな」と、自己嫌悪に陥る事はありません
「ダメな母親でごめんね」親として自信がないあなたへ贈りたい信頼を取り戻す親業メソッド
「子供に申し訳ない」「こんな母親でごめんね」「私ってダメな母親だな」と、自己嫌悪に陥る事はありません
-
 親子関係のプロによる「生徒との関係づくり」の秘訣とは?
先生の仕事や学校環境は、私たちが幼い頃とは全く変わってきています。先生の仕事量の多さがしばしばニュー
親子関係のプロによる「生徒との関係づくり」の秘訣とは?
先生の仕事や学校環境は、私たちが幼い頃とは全く変わってきています。先生の仕事量の多さがしばしばニュー
-
 生徒が言うことを聞かないときの関わり方とは?
叱らずに自律心を育てる教師学の実践法 「生徒が言うことを聞かない」「保護者対応で疲れる」――教師なら
生徒が言うことを聞かないときの関わり方とは?
叱らずに自律心を育てる教師学の実践法 「生徒が言うことを聞かない」「保護者対応で疲れる」――教師なら