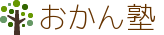教師学一般講座
生徒や保護者との関係をもっとよくする、先生のための対話力向上実践講座

どうやったら築けるの?生徒や保護者との信頼関係
- 子どもの心に寄り添っているけど、しっくりこない
- 生徒に舐められていると感じることがある
- 保護者に詰め寄られてしまうと、言葉に詰まってしまう
- 生徒や保護者の期待に応えられず、自己嫌悪に陥る
- 優しい教師でいられないことに、罪悪感を感じる
力量のある教師になる第一歩、生徒との信頼の架け橋づくり
教師は、子ども達への授業テクニックは学んでいますが、生徒や保護者との信頼関係を築く具体的なコミュニケーションスキルは、ほぼ学べていません。
ここで、多くの教師がつまづき、悩んでしまうのだと思います。
「人付き合いが苦手」「文化や慣習、世代によっても、コミュニケーションのとり方は違うもの」と、半ばあきらめているかもしれません。
ですが、世代や性別、障害の有無にかかわらずに誰にでも応用できる、よりよい人間関係の「考え方」や「原理原則」は存在します。
それらの「考え方」や「原理」を、実際の会話に役に立つような「コミュニケーションの基本技能」に落とし込んで、自分のモノにできる方法論があります。
「生徒が安心して本音を話すようになる聞き方」
「叱らなくても生徒に伝わる言い方」
「子どもと一緒に考え、行動を引き出せる話し合いの方法」
を、習得できる、目からウロコの概念と、言ってみて初めてわかる、コミュニケーションの体験学習があります!
やりがいを感じていたのに苦痛に変わる理由
本来、子どもを教えることは楽しいことです。
自分の持っている「何か」を子どもに教授し与えていくとき、子どもが目をキラキラさせ新しい技術や洞察力を身につけると、これほど「やりがい」を感じる仕事は他にないでしょう。
ですが、それには手間と時間がかかります。
教える「努力」は、報われる時もあれば、挫折、失望することもあるでしょう。子どもは必ずしも熱心に学ぶわけではなく、時に強情に反抗したり、学習意欲を失うこともあるからです。
「あなたたちのためにやっているのよ」「大人になったら、勉強しておけばよかったなと思うはずよ」「やる気さえあれば、力はあるのに」などと言っても、効果はありません。
子どもの為と思っても、子どもが受け容れてくれない時、教師は失望したり、激怒したり、生徒に当たったり、自分の未熟さに気づいたり、惨めな気持ちになります。
あれほど「やりがい」だったことが、逆に「苦痛」に感じてしまう時、、、、
この「成功と失敗の差」は一体何でしょうか??
ここが、コミュニケーションの技量の差なのです。
コミュニケーション技術の基本は、話す場合の話し方と、聞く場合の聞き方です。
何気ない日常会話の話術の中に、プラスアルファの技量が要求されます。この、わずかなコトバの違いから、生徒との人間関係に差が出てくるのです。
生徒と対立した時こそ教師としての真価が問われる
子どもには日々いろいろな「問題」が起こります。また、生徒間の「対立」も起こります。
教室にゴタゴタは付き物です。問題が起こらない教室の方がおかしいのかもしれません。
教師にとって問題への対処はかなりのエネルギーと時間を使いますから、なるべく早く解決しようとしがちです。
そんな時、教師学では、生徒同士で問題解決できるように、成長を効果的にうながす援助の方法を提示します。
子どもは自らの問題を自分で解決する力を持っており、その成長と発達を最大限に促進していく方法です。
また、生徒間の「対立」も、起きて自然だと考えます。全ての経験を彼らの成長の糧に変え、生徒自身の主体性、責任感、規律心、思いやりの成長をうながし、生きる力が育つには、教師の対話力こそをが鍵となります。
状況を見極めて、その場にあった対話が要求されるところです。
でも、例えば、対立といっても、教師が「対立の当事者」である場合と、「子どもたち同士が対立している場合」では、解決のための効果的なツールが異なります。
どの場面なのかを見極めながら、適切に問題解決をすることで、信頼関係を深めていきます。
■実践例
小学校1年クラス担任の先生の実践例を紹介します
☆遊び仲間に入れない (小学校・岐阜・30才)
小学校1年のYとMとの間の対立
Y:「まさ子先生、Mさんね、僕と遊んでくれへんもん。遊ぼと言っても、だめって言うで」
教師:「Mさんに遊ぼって言っても、いいって言ってくれないの?」
Y:「うん。いつもそうや。Dさんとかは遊ぶのに」
教師:「Yさんは、Mさんと遊びたいんだね」
M:「だって、僕、もう他の子と約束したもん」
Y:「ほら、いつもそう言うもん」
教師:「約束を他の子としてしまったから、Yさんとは遊べないの?」
M:「うん。だって、みんなだっているし」
教師:「YさんはMさんと遊びたいって言っているけれど、Mさんは約束をしてしまったからと言うから、どうしたらいいかな。一緒に考えてみようか。このままではお互い、先生もこの辺モヤモヤするから」
Y:「僕、もういい。あきらめる」
M:「僕、約束したDさんとかにいっしょに遊ぼうって聞いてくる」
Y:「本当?」
感想
学校終了後の遊びのことでYが怒って私のところへ来たことから始まった。いじめというのではなく、MやDは保育園からの大の仲良しで自然と遊ぶ約束ができるのに、Yはその後になるためこうしたことが起こる。 以前は「Mさん、そんなこと言わんと一緒に遊んであげてやー」と押しつけていたが、私の言い方も少し変わったと思う。
(親業訓練協会HPより)
生徒や保護者から求められる「理想的ないい先生」が苦しめている
多くの教師が自分なりの理想の教師像をもち、日夜、努力しています。
- 自分は教師なんだから、普通の人より優れていなければならない、
- 理解力があり物知りで、完璧でなければならない、
- 高徳の人にならなければならない、
- 人間的な弱さを超越して公平かつ首尾一貫して共感できなければならない、、
この、多くの教師や親がもつ「理想像」こそ、間違っていると、教師学をつくったゴードン博士は言っています。なぜなら、教師の「人間性」がなくなってしまうからです。
人間が成長する上で大切なのは、正しさよりも人と人としての「温かい心のふれあい」です。
生徒は「正しい先生」よりも「人間らしい親しみを感じる先生」の方が大好き!
一人の人間同士として、お互いを尊重し、歩み寄り、分かり合おうとする「人としての温かい関係性」そのものに惹かれるからです。

☆依頼事を早速やってきた同僚に(専門学校・埼玉・42才)
(前日、教務担当の同僚ABに資料を渡し、実習指導案を考えておいてほしいと協力を依頼した)
A:「先生、昨日、私なりに考えてきたんですけど」
私:「エー、見せてください」
A:「こんな感じで・・・」(3枚も案が書いてあった)
私:「早速有り難うございます。見ていて、私もなんかやる気出てきました」
A:「そうですか?先生忙しいから原案があればやりやすいかなと思って」
私:「嬉しいし、アイデアが湧いてきます。助かりました」
B:「私もこれ、考えてきました」
私:「すごーい。うれしいです。じゃあ。ちょっと話しましょうか」
感想
同僚とは少し距離をとっているところがあったが、これをきっかけに、言葉が足りなかった私、1人で抱え込んでイライラしがちな私に気付いた。3人で実習指導をするので、協力し合うムードが盛り上がり、とてもうれしくなった。
生徒や親への人間関係づくりの原理とメソッド:教師学講座
「知識はあるのに、教室で生かせない」──そんなもどかしさを解消するのがTETです。
教師学(Teacher Effectiveness Training)の6つの特徴
- 信頼できる確かな方法
「生徒を尊重して」「教師も自己表現を」などという「概念」だけをどれだけ学んでも、実践では役には立ちません。それらの「概念」を、誰もが実現可能にする「具体的な方法論」として提示されています。体系的に整理されたメソッドと、具体的な文法により、実践、実現するための方法が明確に提示されています。 - 生徒を発達、成長させるための具体的な方法
生徒の発達・成長という、全ての教育者にとっての目標を実現させる方法です。生徒を依存させたり、未熟なままに抑えるのではなく、生徒が自分で責任を持ち、自ら学び決定し、気分をコントロールし、自己評価できるように、成長と発達を促すための具体的な技術です。 - アメとムチに頼らない方法
アメやムチをつかって彼らをコントロールする方法は、これまでの学校教育ではおなじみのやり方でした。ですが、この方法は生徒によっては反発や落胆を生みます。「支配と面従腹背」表向きには従順なふりをしていても、内心は反発心を育ててているだけ。それでは何の解決にもなっていないのです。 - 年齢・個人差はあってもすべての生徒に通じる方法
生徒は、性別、年齢、知能、能力、家庭の社会的環境、人種などさまざまな差があります。TETの方法は、小学生でも大学生でも当てはまるものです。それは、人間関係の良しあしは、「生徒が教師からどう扱われているかに影響される」と考えるからです。誰もが持つ「人間としての特性や感情、反応」など、人間関係一般の理論に準拠している方法なので、全ての生徒に応用できます。 - 「生徒の規律」の問題をどうするか
生徒にとって大切な「規律の問題」。その重要性はわかっていても、いざとなると頭が回らなかったり、維持させるが困難なのが「生徒の規律心」です。生徒自身が規律心を持つためには、教師のあり方や接し方を「権力や権威」を使わないモノに抜本的に変えていく必要があります。そのためのヒントがあります。 - 権威主義と寛容主義
現状を改革するために問題解決しようとする時、ともすれば、両極端になりがちです。例えば厳格か寛容か?自由か統制か?伝統か進歩か?生徒中心か教師主体か?など。話し合いが熱くなればなるほど、「あれかこれか?」の両極端の対立になり勝ちです。結局は権力争いに逆戻りしてしまうのは、勝者と敗者ができてしまうからです。
TETでは、勝者と敗者ができない話し合いの方法が提案されます。
TETで学ぶコミュニケーションの技能
生徒との信頼関係を築くいくつかのコミュニケーション技能を、いつ、どこで、どんな方法が効果的なのか?それぞれが判断しながら、選択できるように学びます。
- 能動的な聞き方:
生徒が学習上の問題をかかえている場合に、生徒が自分で解決策を見つけられるように手助けする技術 - わたしメッセージ:
生徒のお陰で教師は欲求を妨げられ困っている。君の責任で行動を変えてもらいたいー教師の気持ちを率直に伝える技術です。教師も一人の人間として気持ちを表現することで、生徒の思いやりや規律心の成長を促します。 - 対立を解く:
権威主義でもなく寛容主義でのない。人間関係に欠かせない対立を負けない方法で解く方法です。勝つか負けるかという非生産的な論争に終止符を打つためには欠かせない技術です
講座の特徴
- 生徒が悩んでいる時
- 保護者との面談
- 生徒同士のケンカやいざこざを仲介する方法
- 生徒の反論にどう対処するか?
- 同僚との関係
- 教師として保護者とどう接するか
- その他
世界中で500万人以上が実践してきた方法。
受講した教師の実践事例
子ども間の対立を解決する介入的援助法
肯定のわたしメッセージで温かい関係を深める
■実践例
教師学では児童・生徒理解とともに、子どもたちが教師の気持を理解できるような「教師の自己表現が大切である」と考えます。ですから、「教師による生徒理解」と「生徒による教師理解」をともに大切にしながら相手に関わる心構えを「教師学マインド」と呼んで強調しています。
自己表現の方法として教師学は「わたしメッセージ」を提案していますが、それには、私の考えや信念を伝える「宣言のわたしメッセージ」、将来満たしたい私の欲求を伝える「予防のわたしメッセージ」、相手の行動に対する私の否定的な感情を伝える「対決のわたしメッセージ」、相手の行動を受け入れている私の肯定的な感情を伝える「肯定のわたしメッセージ」の4種類があります。
最後の「肯定のわたしメッセージ」は、子どもたちとの心の絆を強めていく上でとても効果的なものです。学校では教師は管理者として生徒に「対決」しなければならない場合も多くありますが、それ以上に子どもたちに助けられ、子どもたちの行動を受容する場面も多いのではないでしょうか。
そんな時、「君はそのままでいいんだ。私は君を受け入れている」というメッセージを子どもたちに言語化して送ります。「肯定のわたしメッセ−ジ」は相手に大きな影響を与えるメッセージです。
受講生の感想(親業訓練協会HPより)
自分は以前、高校・中学で美術の教師をしていました。中学校に勤めた時に、荒れている学校に配属され、他の先生方は厳しめの指導をしており、自分もそれに合わせた指導(第一法的な指導)をして、生徒との関係が上手くいかなくなったことがありました。
その時にすでに「教師学」のことは知っていて、本も読んでいたのですが、上手く実践できていなかったことに気付き、講座を受講しました。
今は学童クラブに勤めており、能動的な聞き方やわたしメッセージを使って、子どもたちとの関係を築いてきましたが、次第に問題なし領域が広がり、普通のやり取りでも、こどもが素直に言うことを聞いてくれるようになり、驚いています。
今では特に大きな問題がある時に、教師学の手法を使うようにしていますが、その時も、子どもたちの行動が変わっていく確率が高いと感じます。勝負なし法(第三法)は、色々困難がありますが、機会があれば実践し、追究していきたいと感じています。
理論を机上で学ぶのではなく、たくさんのロールプレイやブレインストーミングなどの話し合いで、楽しく身についてきている気がします。
思ったことを書く前に、人と話をしてみることや、相手のことにじっくりと耳を傾けようとすることで、異なることに気づく体験型、参加型の方法のよさに感動しました。
自分の意のままに相手を操る、そんなノウハウではなく、自分も相手も束縛から解放されて、生きることが楽になるような講座です。たくさんの先生方にこの理論を広めたい。そして日本の子どもたちの未来が子どもたちの手でよりよく切り開かれるよう今の自分に出来ることをやっていこうという気持ちになれました。
息子は高校一年生。爆発的な感情の変動を見せた中学の3年間は過ぎた。親業は知ってはいたものの、なかなか受講することに困難を感じていましたが、思い立って昨年親業訓練一般講座を受けました。
親子関係は激変。扱いにくい子というレッテルを、私は息子に貼り続けていたことに気づき、本当に申し訳ない気持ちになりました。今まで私は、息子の何を、どこを見てきたのであろうか・・・・息子も素直に自分の気持ちを表現してくれるようになりました。
しかし、非常に気持ちも楽になり、息子との関係が良好になったものの、中学1年より他県で寮生活を過ごしている息子との価値観の対立は私の大きな悩みとなっていました。時間的に制約もありますし、頭ごなしに力を使うことなど全く効果のない年頃です。今回教師学講座を受講し、価値観に影響を与えるわたしメッセージを学ぶことにより、“親としてこういうことを大事に思っている”といった親の思い伝える術を得られた思いです。これから息子へいろんな事を伝えられるのが楽しみになってきました。あくまでその実行(主導権)は息子にある事を忘れないようにしながら、息子と新たな関係を築いていきたいと思います。
教師学講座を受講して「自分が教師として大切にしたい想い」をよりクリアーにできたと感じています。そしてそれを実現する方法を学べたことは、これから教師として子どもたちに接する際に大いに役立っていくと感じています。
大学院を修了し、4月から中高一貫校の非常勤講師として働きはじめ、教える立場に戸惑い、生徒の前でもどこかオドオドしてしまっていました。「教師」という権力を使って従わせることに抵抗を持ちつつも、どこか「生徒より優位でいないといけない」という意識があったように思います。
教師学を学んでからは、生徒が不満をぶつけてきても「その奥の気持ちを見よう」、「しっかり受け止めよう」という余裕を持てるようになりました。また、生徒に対して自己表現をする時に感じていた恐怖がなくなり、のびのびと授業ができるようになりました。
まだまだ、学んだことを活かしきれてはいませんが、教師としてでなく対等な一人の人間として、生徒に憧れ・尊敬してもらえるような教師になりたいと思います。そして、生徒が私との出会いを通して、前向きに、意欲的に人生を歩んでいけるといいなと思います。そのための具体的なコミュニケーションのヒントについて、教師生活1年目の夏に受講できたことは、とても意味のあることだと感じています。
「行動の四角形」を親業で初めて知り、意識して使ってみると、相手や自分に対する感性が研ぎ澄まされてきたような感覚を得ています。問題を所有していることを否定せず、評価もせず、事実としてそのまま受けとめると言うことは、上手く表現できませんが、相手を信頼すること、また、相手や自分を尊重することに、次第につながってきたように思います。
自分の感情をグッとつかんで、わたしメッセージで表現してみる。そこには「褒めなくてはならない」「教師は十褒めて一叱るべし」などの、自分を縛るもの、見せかけようとするものは何もなく、ありのままの偽りのない、本物の私の思いがある。それを表現してみると、不思議と子ども達が真剣な表情で聞いている。そして行動が変わっていく。私の思いを聞いて行動を変えてくれる子ども達に、愛情や信頼感が増していく。そのことを肯定のわたしメッセージで子ども達に伝える。こんなふうにして子ども達と私との関係は、全体として明るく信頼感のあるものになってきました。
去年は教師としての自分に自信をなくし、辞めた方がいいのではないかと悩んでいましたが、「教師学」と出会い、自分がこれから先も教師の仕事の誇りを持ってやっていけるという自信と安心を得ました。苦しい状況の中でも、よりどころとなる考え方や方法を使って、きっとやっていけると、自分の力を信じることができます。受講して本当に良かったと思います。
これからは、せっかく学んだ「教師学」の理念や方法を錆びつかせないように、しっかり使って、感性を高める努力をし続けていきたいと思います。
4日間を通して、とても多くの学びを得ることができた。
行動の四角形に生徒の行動を整理する方法を学んだことで、自分が担うべき問題と生徒が担うべき問題とをしっかり区別することができるようになった。これまでは、生徒が対処しなければならない課題を自分で背負って苦しくなってしまったり、逆に生徒たちに考えさせる時間を与えずに勝手に理解したつもりになって満足してしまっていたことが多々あったことにも気づかされた。これまで、教師として“生徒の前では絶対的な存在でなければならない”、“常に進む道を示さなければならない”と肩ひじを張ってきたが、“生徒とともに解決策を探っていけば良いんだ”、“素直に自分の感情を交えて、わたしメッセージを出していけば良いんだ”という学びは、とても気持ちを楽にしてくれた。
学校では課題が山積みだが、新学期から気持ちを入れ替えて、張り切って生徒と向き合っていきたいと思う。講座で学んだことを少し時間をかけて自分の中で整理し直し、日々の現場で実践していきたい。
これまでの生徒との関わりを見直すとても良い機会となった。
教師学一般講座 概要
受講資格
参加人数
4名〜で開講します。
講座時間と受講回数
全28時間の講座です。
1日7時間の授業を4日間受講していただく内容です。
教師学講座は、補講制度はありません。
主な内容
セッション | テーマ | 詳しい内容 | |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 第1セッション | 目標設定 教師と生徒が対立した時 | ・自己紹介 ・教師学で学ぶこと ・目標設定 ・ロールプレイ |
| 第2セッション | 問題の所有者とは | ・話し合い① ・行動の四角形とは | |
| 第3セッション | 環境改善 コミュニケーションの図式 | ・注意を向ける ・効果的な聞き方とは ・能動的な聞き方の体験 | |
| 2日目 | 第4セッション | 生徒の心を理解するために | ・能動的な聞き方 ・ロールプレイ ・能動的な聞き方おかしやすい誤り・介入的援助 ・ロールプレイ |
| 第5セッション | 教師の自己表現 | ・ロールプレイ ・あなたメッセージとわたしメッセージ ・肯定的な感情を伝える ・否定的な感情を伝える | |
| 第6セッション | 教師の自己表現 | ・生徒と対決する時 ・ロールプレイ ・抵抗されたら ・ロールプレイ ・ロールプレイ | |
| 3日目 | 第7セッション | 対立について | ・欲求の対立を解く方法 ・ロールプレイ ・ロールプレイ ・ロールプレイ |
| 第8セッション | 欲求の対立を解く 価値観の対立 | ・ロールプレイ ・力とは ・ロールプレイ | |
| 第9セッション | 価値観 価値観の対立を考える | ・価値観の模範 ・違いを体験する | |
| 4日目 | 第10セッション | 行動の四角形 援助の方法 プロセスコンサルタント | ・能動的な聞き方 ・ロールプレイ |
| 第11セッション | 第三法の復習 援助の方法 | ・ロールプレイ ・ロールプレイ | |
| 第12セッション | 行動の四角形のチェック 講座の評価、感想、アンケート 修了式 |
ご準備いただくもの
・筆記用具
・昼食(集中講座の場合)
会場
開催場所は、日程や参加人数により、変更になります。ご了承ください。
講師
参加費
| はじめての方 | 60500円 |
|
| 再受講の方 | 35000円(+税) | その他に親業訓練協会費4000円(+税)がかかります |
お申し込みについて
子どもが持つ力と教育の力を信じる毎日を
「生徒が安心して学べる学級をつくる教師」
「保護者から信頼され、建設的に協力関係を築ける教師」
「職員室で振り回されず、自分の教育観を大切にできる教師」
講座スケジュール
2/ 9 月
3/ 28 土
2/ 1 日
2/ 3 火
2/ 11 水
〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西2-3-14 8F
(水・土・日・祝日は休み)
tel 03-6455-0321(10:00〜17:00)