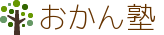- ホーム
- 今日のおかん塾
今日のおかん塾
- 受講生の感想
- コラム
- 講座レポート
- はじめての方へ
- 事例
- つぶやき
- 辛口
- 高校生
- 中学生
- 小学生
- 幼/園児
- 発達障がい
- 聞き方
- 育児の原則
- ネット依存
- 成績不振
- 育児の自信喪失
- 癇癪・ぐずり
- 心身症
- 過干渉
- 会話ができない
目からウロコ!なのはあなたの中にあることだから
2025/10/26
親業ゴードンメソッドの基本となる、「自分の気持ちの整理のしかた」から学びます。
「行動の四角形」という「概念」であり「ツール」です。
これが、ゴードンメソッドの、かなりユニークなところです。
他の子育て系の講座とは、
全く違う考え方だから、
ほとんどの方が戸惑うところかもしれません。
何度か説明しても、
わかっているようで、
微妙にわかっていない?(笑)
…
幼稚園に「体操服で行きたくない」と泣き叫ぶ時、本当の理由はそこじゃないかも?
2025/10/15
何が「むずかしさ」だったかというと、結局は「意志疎通」が上手くできなかったことです。
子ども達が、幼稚園時代、小学校時代、中学生、高校生と、まあ、色々と葛藤を体験してきました。特に二男はやりにくいと感じました。
一番つらかったのは、2歳から3歳ぐらいにかけて、よくわからないところで「泣く」「わめく」「…
兄弟喧嘩はどうしたら無くせるの?兄弟関係も親の関わり方次第
2025/10/10
目の前で「喧嘩」をされると、これっていつまで続くの?と、ハラハラドキドキ。
一刻も早くやめて欲しいのだけれど、どうしたらいいのか?対応に迷う事もありますよね。
我が家は男の子が3人。2学年違いの年齢差もあまりない兄弟でしたから、放っておくと喧嘩が勃発しそうです。なので、ここはしっかりと先手の対策していましたよ(笑)
兄弟喧嘩は、慣れていない…
兄弟の仲がどうしたらよくなるか?
兄弟げんかはとても気になりますが、いつも私がけんかの仲裁などしたくない。
私の老後の為にも(笑)、できれば、仲の良い兄弟でいて欲しい。
その為に、兄弟げんかは「兄」と「弟」の問題とすることを大事にしていました。
具体的には、親が仲裁に入らないことに徹底することです。
現状
兄ーおかんー弟(兄弟の中に母親が入るパターン)
↓↓↓
兄ー弟(母親が中に入らないパターン)
めざすのは、兄弟それぞれがお互いの立場や違い、良さを尊重し合える、兄弟LOVE愛を築くこと!
その1・兄の自尊心を壊さない
対等で納得し合える兄弟関係を、彼らが作っていくために…
私が心がけていたことは、まずは「お兄ちゃんを立てる」ことです。
私は、兄弟は1つの社会のはじまりだと考えました。兄弟の仲で育まれる社会性みたいなのがあるのかなと。
それで、長男の権限をちょっとだけ強くして、彼をいつも立てていました。
ですが「ケンカの度にいつも母親がかばっている弟」のことなんか、誰が面倒を見てやろうと思うでしょうか?なので、長男の内面から生まれる弟への感情を大切にしたいと考えていました。
だから、兄が「弟をかわいがろう」と思えるように、弟たちが「お兄ちゃんってすごいな〜」って思えるように、できるだけ自然に思えるように、仕掛けてました(笑)
例えばお菓子をあげるときも長男に全部預けて「3人で分けてね、、」とか(笑)
こう言うのって、母親のちょっとした心遣いでガラリと変わると思うんです。
そして、こんな風に考えたのです。
もともと、第1子は、両親の愛情を100%一人占めしていました。なので第1子長男にとっては100%が当たり前
ところが、第2子が生まれてからは、それが他人の都合で100%でなくなった
なので、第1子にとっては第2子は、親の愛が 100%→50% に減らされた原因になる
逆に第2子は、親の愛情がはじめから「50%」しかないのだけれど、第2子にとってはその状態が「フツー」でそれしか知らないので、それが全て、すなわち100%
さらに 我が家は第3子が産まれ
生まれながらにして、親の愛は1/3・・なんと33%。親から見ると可哀想ってなるかもしれませんが、でも、彼は、その状況しか知らない
つまり、33%であっても、三男にとってはそれが100%おまけに、長男や二男からも、多少なりとも可愛がってもらえる?
このようによーーく考えてみると 「親は第1子に少し優遇してあげても、大丈夫なのかな?」って思ったんですね。そして「その方が、断然兄弟が仲良しになる!」って思いました。愛情のシャンパンタワーを、長男から徐々に満たしていくイメージです。
これは我が家でのケースですが、私が伝えたいのは 親が考える「平等」「公平」と、子どもが考える「平等」「公平」は違うということです。
兄弟は、発育段階が違いますし個性も全然ちがいます。親の立場も状況も全く違うのです。そして考え方が全く違います。なので「兄弟は平等に扱おう」という考え方は、ナンセンス!!!と言うか、所詮ムリなことなのだと思いました。
その2:ケンカを善悪で裁かない
兄弟げんかが起こると、親はよく「誰が悪いか?」とか 「誰から先に手を挙げたの?」とか「現場検証」を始めて「公平に裁く」をしようとしませんか?
ただ、ここで親が兄弟を「裁く」必要はないのかもしれない(笑)
大人の世界は、「裁く」ことが当たり前です。でも子どもの成長を考えるとき、大切なコトは彼らを「裁く」ことなのでしょうか。そうではなく、相手を思いやる気持ちを「育てる」ことをしたいのではありませんか。
私は、子どもたちに教えたかったのは「何がなんでも喧嘩をしない」ということではありませんでした。それは仕方がない事もあるでしょう。ただ、ケンカをすることではじめて経験できる、後味の悪さは知って欲しいと思いました。
「ああ、悪かったな」
「 あいつにも、言い分があったのかもしれないな」
「ケンカはいやだな」
「どうやったら、仲良くなれるのかな」
ケンカをするということは、きっと彼らに「守るモノ」があったのでしょう。そして、それを守るために「失うモノ」があるはずです。ケンカには、リスクがあるのです。
守るモノと失うモノをどちらも経験したうえで「次はこうしよう・・・」と、本人自身が考え、判断し、自分を律することができる、そんな風に自ら考えるようになってくれたらいいな、と思いました。
大切にしたいのは、子どもに考えさせるということです。
- 自分の気持ち
- 相手の気持ち
- 自分はどうしたいのか?
- 何が嫌だったのか?
- どうすれば、もっと良かったか?
困っているのは、自分の気持ちを抑えきれずにリスクを冒した「子ども」です。この経験を活かしたい!そのためには「代償」を自分で感じることが必要なのかなと思いました。子どもが問題を持っている時は、親が問題を取り上げない事が一番の成長の近道です。
その3:解決策を親に頼らせないで中立を保つ
子どもはとにかく、親の態度に敏感です。 親が「なんとかしてくれる」と思うと、ずっと頼ってきます。でも、親は「何もしてくれない」とわかると、あまり頼ってこなくなります。
もしも、親が今まで喧嘩の仲裁をしてきたのなら、子どもは当然のように、
と言ってくるかもしれませんね。
私はいつも「あなたはお兄ちゃんに叩かれてイヤなのね、、、、」でオワリにしていました(笑)
もし「なんとかしてよ!」と頼まれても「だって、お母さんは現場を観てないから、何とも言えないわ」「それは知らないよ」「ふーーん、」ほとんどの場合、そう言って仲裁を断っていました。動く素振りは見せていません。
その代わり、とにかく気持ちはしっかりと聞いていました。どんな否定的な感情を言い出しても、非難することなく受け止めていました。
聞き方は、親業で習っていました。これをしてあげると、次第に落ち着いてきます。そして、兄弟関係もとても客観的に考えられるようになりましたよ。
こんな子育ては、予想以上に効果があったように感じます。
本当に仲良し兄弟になり、わたしもラクでした♪
兄弟がげんかを繰り返す時には、別の理由が隠れているかも
兄弟げんかがひどくて何度も繰り返されている場合、本当の理由は違うところにあります。それは、ほとんどの家庭では「親のモノサシ」の下で、兄弟が比較・評価されていることです。
兄弟が比較、評価されている時は、本当に仲が悪くなります。
子どもは暗黙のうちに親のものさしを基準にしながら、比較されているので、そこでどっちが優れているか?競争が起こります。
つまり、比較・競争を強いられている環境では自然に「攻撃型」のコミュニケーションパターンを使っていて、その結果ケンカが絶えないということになります。
家庭の中が「親のモノサシ」だけでなく「自分のモノサシ」をそれぞれ持つことができると、家庭内でよくある、勢力争いの喧嘩は起こりません。
子どもや家族全員が対等な存在としていることが許されていると、それぞれが自分のモノサシをもつことができますから、争いはぐっと減ります。
【参考記事】母親のコトバが心を作る!知っておきたい一言の違いと引き算のすすめ
兄弟は社会のはじまり、人間関係のトレーニングのチャンス
兄弟は、社会のはじまり。そして、一緒に育つ「仲間」でもあります。
動物も、幼少期はじゃれあって、喧嘩しあって育つ方が社会性が育つと言われています。私は人間も全く同じだなと感じます。
幼少期の兄弟げんかは、人間関係のトレーニング!
スゴイ声で喧嘩されると、大きなストレスになりますが、兄弟を通じて、人間関係の繋ぎ方を自然に身に付けるように感じます。
そして、親が一人ひとりの子どもに合わせて関わり方をしていると、自然に落ち着いてくるようです。親があれこれ考えなくても、子どもは素晴らしい能力を持っていますので大丈夫。
自分で考えて、策を練ったり、あきらめたりしながら、兄や弟との関わり方を自然に身につけていきます。
こういうことを、家庭で丁寧に経験しておくことは、将来の豊かな人間関係のためにとても大切ではないかな、と思うのです。
【参考記事】兄が弟に嫉妬しないのは、自分が愛されている確信があるからです
親業訓練一般講座 第80期が開講しました
2025/10/06
今回の講座も、子育ての立場や過程、年数も違う4名の受講生さんたちが、集まりました。
親業訓練一般講座は、子どもとの心の架け橋づくりを学ぶ、基本の講座です。
基本の3つのスキルがあるのですが、それらを「頭」でなくて、実践的に身につけるための講座ですよ~
受講生の方同士の話し合いなども多く、みんなで考えながら学ぶので、あっという間の講座…
-
 おかん塾の子育て
3人の息子がいても、いつの間にか“親バカ”になれた秘訣
おかん塾の子育て
3人の息子がいても、いつの間にか“親バカ”になれた秘訣
-
 講座レポート
「え?こんなに違う?」目からウロコの講座レポート満載 おかんの仕事は365日24時間(-_-;)ずっ
講座レポート
「え?こんなに違う?」目からウロコの講座レポート満載 おかんの仕事は365日24時間(-_-;)ずっ
-
 つい怒ってしまうから抜け出す3日間
おはようございます。今日は、朝から整形外科クリニックの診察に行ってきました。実は、先日の1月15日に
つい怒ってしまうから抜け出す3日間
おはようございます。今日は、朝から整形外科クリニックの診察に行ってきました。実は、先日の1月15日に
-
 主体的で自由な大人の学び
親業訓練講座は全8回です。毎回、宿題が出ますが、提出は「自由」です。大人の勉強は強制されることはあり
主体的で自由な大人の学び
親業訓練講座は全8回です。毎回、宿題が出ますが、提出は「自由」です。大人の勉強は強制されることはあり
-
 「勉強しない高校生へ」しっかり啖呵を切れる母になろう
親業訓練講座の第4回目のレッスンが終わりました。 3週間ぶりの講座だったので、みなさんは「お久しぶり
「勉強しない高校生へ」しっかり啖呵を切れる母になろう
親業訓練講座の第4回目のレッスンが終わりました。 3週間ぶりの講座だったので、みなさんは「お久しぶり
-
 子どもを変えない子育てが、子どもを変える理由
今日は、夫のお休みの日。念願の廣田神社(兵庫県西宮市)にお参りに行ってきました。私が捻挫をしちゃった
子どもを変えない子育てが、子どもを変える理由
今日は、夫のお休みの日。念願の廣田神社(兵庫県西宮市)にお参りに行ってきました。私が捻挫をしちゃった
-
 塾に払うお金がもったいないからやめてくれる?と言いたい時
塾にいかない、サボる「行く行く」と言いながら、「行かない」「止めたら?」というと「止めたくない」と
塾に払うお金がもったいないからやめてくれる?と言いたい時
塾にいかない、サボる「行く行く」と言いながら、「行かない」「止めたら?」というと「止めたくない」と
-
 親に何も言う気がしなくなる12パターンの言い方
親が言ってないつもりでも、言っている「小言」子どもが話しをしない、話しかけても、スルーされる、調子の
親に何も言う気がしなくなる12パターンの言い方
親が言ってないつもりでも、言っている「小言」子どもが話しをしない、話しかけても、スルーされる、調子の