「褒めて育てる」ってどうなの?みんな知らない「評価」のリスクを徹底解説
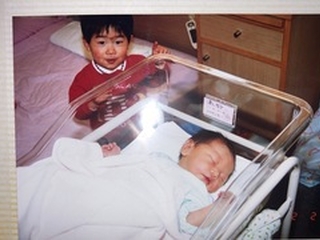
子どもの自己肯定感を高めるために、子どもに自信をつけさせるためにも、「子どもを褒める!」は現代のお母さんたちの常識といえるかもしれません。
昭和に生まれた私は、子ども時代は熱血指導が全盛期でした。巨人の星やアタックナンバーワンを観て育ち、もちろん、親にはそれほど褒めてもらえませんでした。
そして、昭和世代で自己肯定感の低い人とは「親に褒められていない人」だと信じていたんですね。
親業や心理学を学ぶまでは。。。
だから、まさか「評価の子育て」に、リスクがあるなんて、思ってもいませんでした。親業を学び始めて、褒めコトバを子どもに浴びせ続けていく事で、子どもの心に起こる作用を知った時に、愕然としたんですよ。
褒めコトバには、子どもの健全な心の成長に与える弊害があったのです。
私は、社会で「評価」されると、自分の価値が認められたようで、とにかく嬉しいし、承認されたい欲求は、他人から「評価」されることで満たせるものだと、普通に思っていました。でも、この考え方も子育てにおいては注意が必要だったんですね。
敏感な子どもがどう受け取っているか?
コトバはいつも、受け取った人の「感じ方」で解釈されます。
つまり、親のコトバが必ずしも子どもにそのままの意味で伝わっているとは限りません。そして、人は、自分以外の何者かに支配させられそうなとき、心に違和感を覚えます。
自分の行動は自分で決めたいのです。なので、誰かから「支配」されたり、「コントロール」されるのが好きではありません。
「支配」「コントロール」というのがキーワード。
どんなに素晴らしい「賞賛」であっても、子どもが「自分が強制されそうだと感じた」なら、子どもにとっては「心理的に自由でなくなる」という事ではないでしょうか。
弊害のある褒め方とは
本当に感動の気持ちで表現するなら、それほど悪くないかもしれません。
ただ、「褒め言葉」をかける時には、「その行動を次もさせたい」という、親の意図が潜んでいる場合がほとんどだと思います。
それが「支配」「権力」だなんて、誰も思ってもいないかもしれません。
ですが、子どもにとって、親は時別な存在。大好きな母親の愛情を得るために、母親のちょっとした言葉から「あ、お母さんはこういう子供に育ってほしいんだな」「理想的な子どもはこういうこどもなんだな」と感じ取ります。
それは、親に褒められたい、という子どもの根源的な欲求です。
あからさまに親の「鋳型」を押し付けられた場合の方が、子どもは反発したり、逃げたりできます。
ですが、それが、巧妙に仕掛けられた「鋳型」だと、長い月日をかけていつの間にかじわじわと侵食されるように自己を明け渡してしまい、結果的にいつも親の価値基準で生きたり、いつまでも依存的だったり、やりたいことが見つからない子どもに育つリスクが高まります。
それが、親も知らない間に起こってしまう、、、、というところがとても恐ろしいところなのです!
親は、子どもの依存性を育てて、自己規律力・自己評価力を育てていないなんて、、、
これって、親は良かれと思ってやっている行為ですからね。
なので、親は子どもの元気が急になくなってしまった時に、どうしてそうなったのか、全くわからないのです。
大人と子どもの決定的な違い
大人は感じないけれど子どもにとっては大きい力を感じる場合があります。
心理的に弱い立場の人、子ども、生徒、患者さんは、力の差がある人からのちょっとした言葉に敏感です。
つまり、自分が思う以上の影響力を与えてしまう、ということ!
親はもっと自分の立場や子どもからとてつもなく愛されていることを自覚する必要があると思います。
心理的に強い立場の人が持つ力について、よーーーーく理解しておかないと、知らないうちに関係が壊れていっちゃう??ってことがあるのです。
人間関係における心理的な「力」とは何でしょう?
ココが曖昧だと、わかったようでわからないままかも知れませんね。
人間関係は実にシンプルです。
ほめコトバの弊害アレコレ
たとえば、優秀な兄弟を持つ人など、兄弟がほめられていたことで、自分の能力が足りないことを非難されていたように感じて、深く傷ついていることがあります。
ほめコトバは、ほめられない人にも影響を与えています。
非難したり罰してるわけではないけれど「評価する」ってそういうことです。
これも、ほめ言葉のリスクとなると、ゴードン博士は説いています。
ゴードン博士は、
「アメとムチを使った子育てで、責任感や主体性など育たない」と、バッサリです(笑)
幼少期ではOKだったことが、思春期にNGになるのは、本人が悪いのでも親の性格が悪いのでもなく、ただやり方が間違っているだけの問題です。
でも、びっくりするほど、納得しませんか??
褒めると伸びるは正解だけど、、、
確かに、ほめると、子どもは伸びると思います。
嬉しくて、やる気がモリモリ~
「あの子は小学生時代が華だったな」
「その後はパッとしないな」
なんて、そんな人生を自分の子どもに生きさせたくありません!
評価とは?
ほめるとは?
リスクは?
ほめるとか、ほめないとかの問題でなくて、親の力、権力について、様々な視点で考えていくと、いいのかもしれません。
子どもの成長にリスクの少ないコトバを遣おう!
親になれば、ずっと関わっていくことになる「子どもとの人間関係」だから、原理・原則から学んでいくのがおすすめです。
親だって、子どもをコントロールしたいわけじゃないものね。
